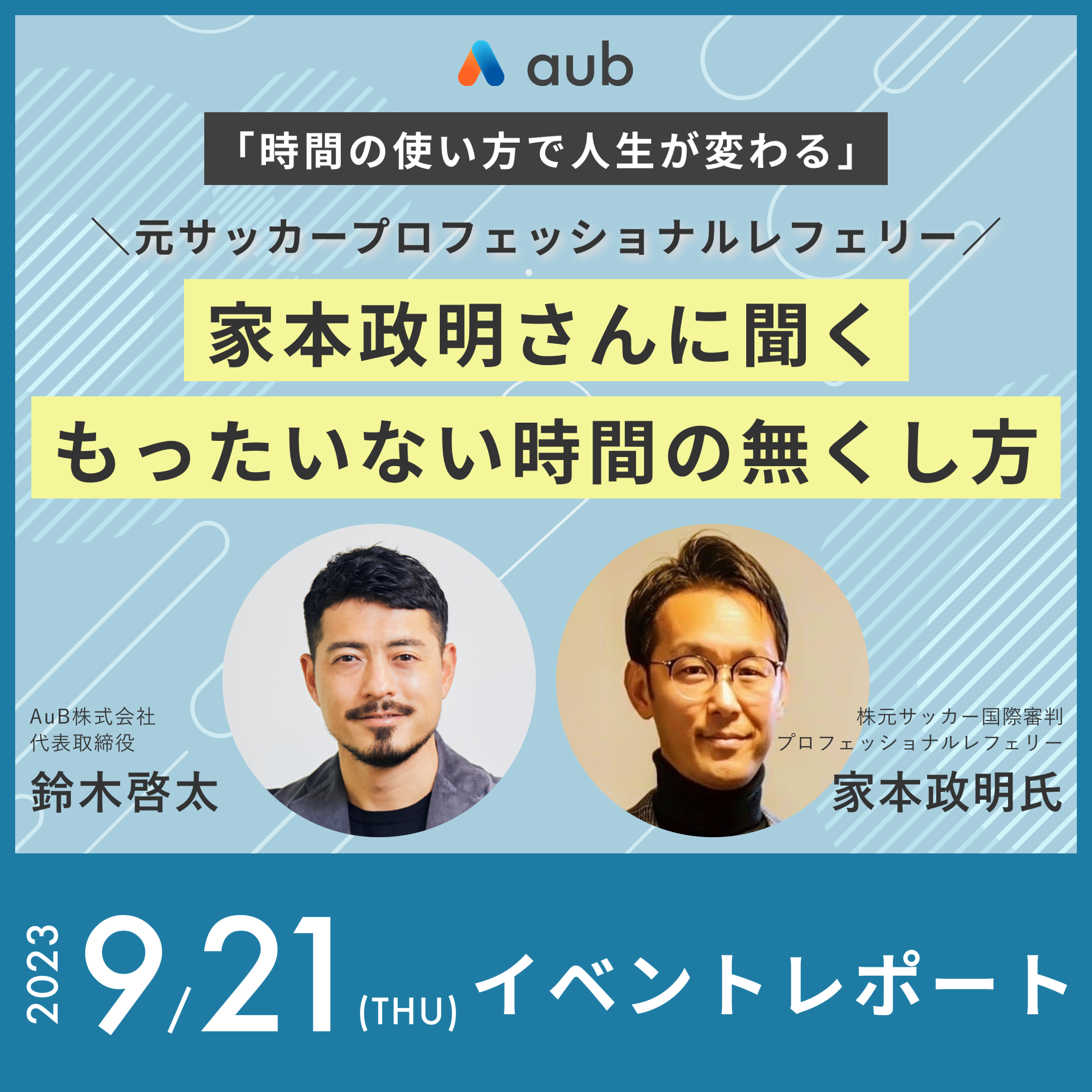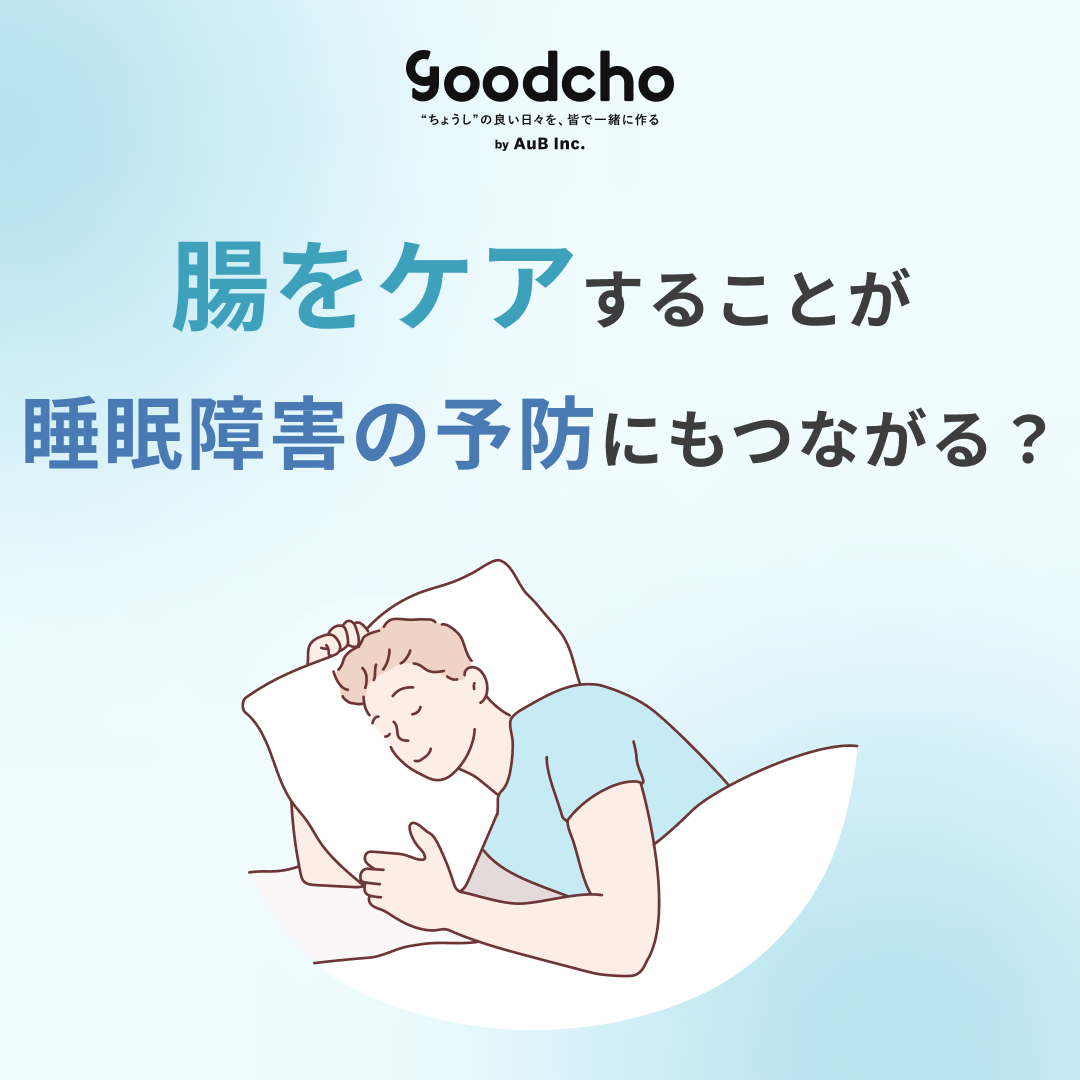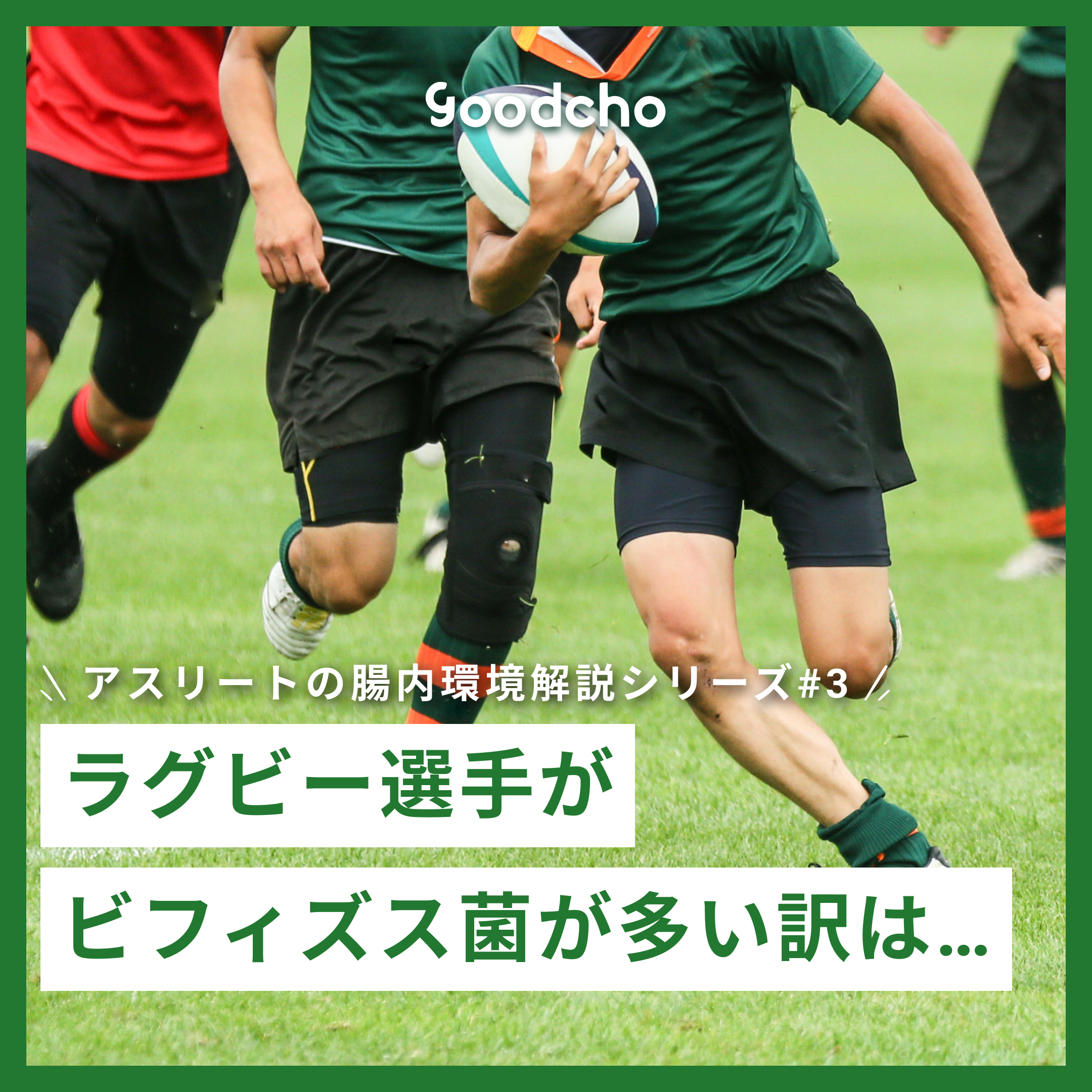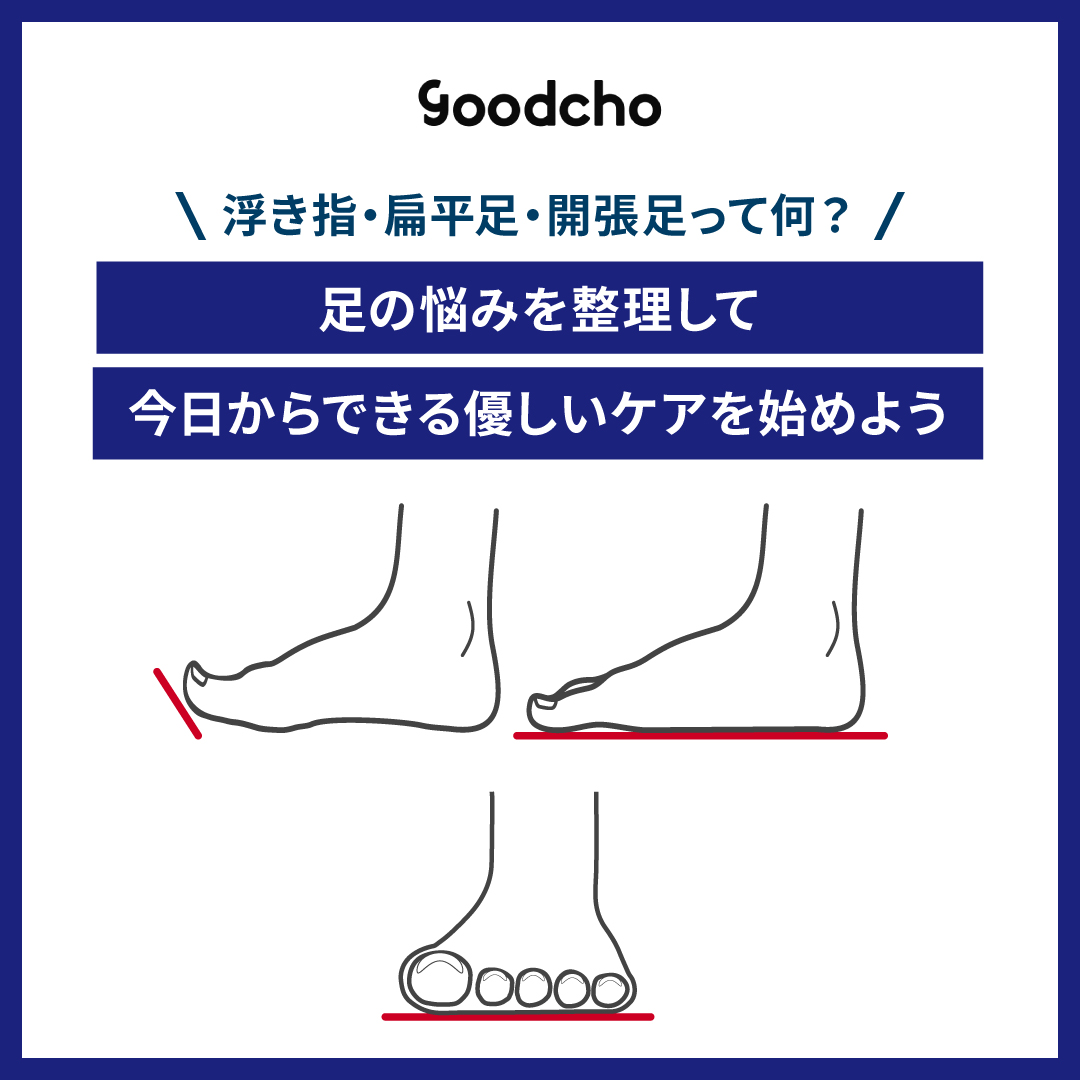日本が世界に誇る「和食」は、味噌や醤油などの発酵調味料が欠かせない食文化です。なぜ、古くから親しまれてきた発酵食品がいま改めて注目されているのでしょうか。その背景には、保存性や旨味だけでなく、健康面で期待される数々のメリットがあります。本記事では、発酵食品の歴史とともに、和食の魅力が注目される理由を探っていきます。
発酵食品の基礎と歴史

発酵食品とは、微生物の働きを利用して食品を保存しやすくしたり、風味・栄養価を高めたりしたものです。例えばチーズ、ヨーグルト、キムチ、味噌などは、いずれも微生物の発酵力が大きなポイントとなっています。
もともと冷蔵技術がなかった時代に、長期保存の知恵として世界中で発展してきたのが発酵食品です。日本農林水産省の資料によると、発酵の利点としては「保存性」「栄養価」「風味・おいしさ」の3つが挙げられています。(*1) 余った作物や魚、肉を塩漬け・燻製する過程で、自然発生的に「発酵」という現象が見つかり、そこから食品文化が広がったとされています。
発酵食品が世界中に広まった理由
保存技術としての必要性
食料を腐らせずに貯蔵する目的で、塩や麹、酵母などを活用した。
独特の風味や味わい
乳酸菌による酸味や、熟成による深い旨味が食欲をそそり、好まれてきた。
健康や栄養面の付加価値
ビタミン類の増加や消化吸収の助けになるなどのメリットが分かり、世界中で日常的に取り入れられるようになった。
和食と発酵食品

2013年にユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」は、四季折々の食材を活かし、栄養バランスに優れる点が評価されました。なかでも、味噌や醤油、酢、日本酒、みりんなどの発酵食品(あるいは発酵調味料)は、和食に欠かせない存在です。
実際、日本独特の麹を使った製法は、欧米の乳酸発酵・チーズ製造などとは異なる発展を遂げています。例えば味噌は、大豆と麹菌を合わせて熟成させることで独特の深い香りと旨味が生まれます。醤油も同様に、大豆・小麦と麹菌の発酵・熟成を経て得られる調味料です。
和食が注目される理由
健康への影響
塩分が高い味噌・醤油でも、発酵過程で生まれる成分が血圧や血糖値に良い影響を与える可能性が示されています。(*2)
少ない動物性脂肪で豊富な旨味
旨味成分を上手に使うため、脂肪分の多い食材に依存せず、結果的に低カロリーでも満足感が得られやすい。
長寿社会との関連
世界的にも珍しい長寿国である日本の食文化として、和食の摂取が健康維持に関係していると海外からも注目されている。
発酵食品が再評価される現代の背景

現代社会で再び発酵食品がブームになった理由として、以下のような観点が挙げられます。
腸内環境への関心の高まり
近年「腸活」という言葉が流行し、発酵食品が腸内細菌に与えるメリットが科学的に示されるようになりました。
生活習慣病の増加
肥満、糖尿病、心疾患などが増える中で、比較的ヘルシーな食生活へのシフトが求められている。
グローバル化による料理の多様化
世界各地の発酵食品が手軽に入手できるようになり、日本の味噌や醤油も海外で人気を博している。
和食を暮らしに活かすコツ

和食は発酵調味料を多く使うため、家庭でも取り入れるハードルがそれほど高くありません。例えば、
毎朝の味噌汁
簡単に作れるうえ、大豆由来の発酵成分を摂取できる。具だくさんにすることでビタミン・ミネラルを補える。
醤油、みりん、酢の活用
煮物や炒め物、ドレッシングなどで使うことでコクが増し、塩分控えめでも満足感が上がる。
納豆や漬物
一品プラスするだけで、腸内環境をサポートする発酵食品を気軽に摂りやすい。
まとめ
発酵食品は人類が古くから培ってきた「保存」と「おいしさ」の知恵です。そのなかでも麹菌を活かした和食文化は、ユネスコ無形文化遺産に登録されるほど独自性と健康的メリットが評価されています。現代においても、腸内環境や生活習慣病の観点から、発酵食品を上手に取り入れる食生活は注目の的です。まずは毎日の食事に味噌や醤油といった伝統的な調味料を活かしてみてはいかがでしょうか。きっと体の内側から、元気とおいしさを実感できることでしょう。