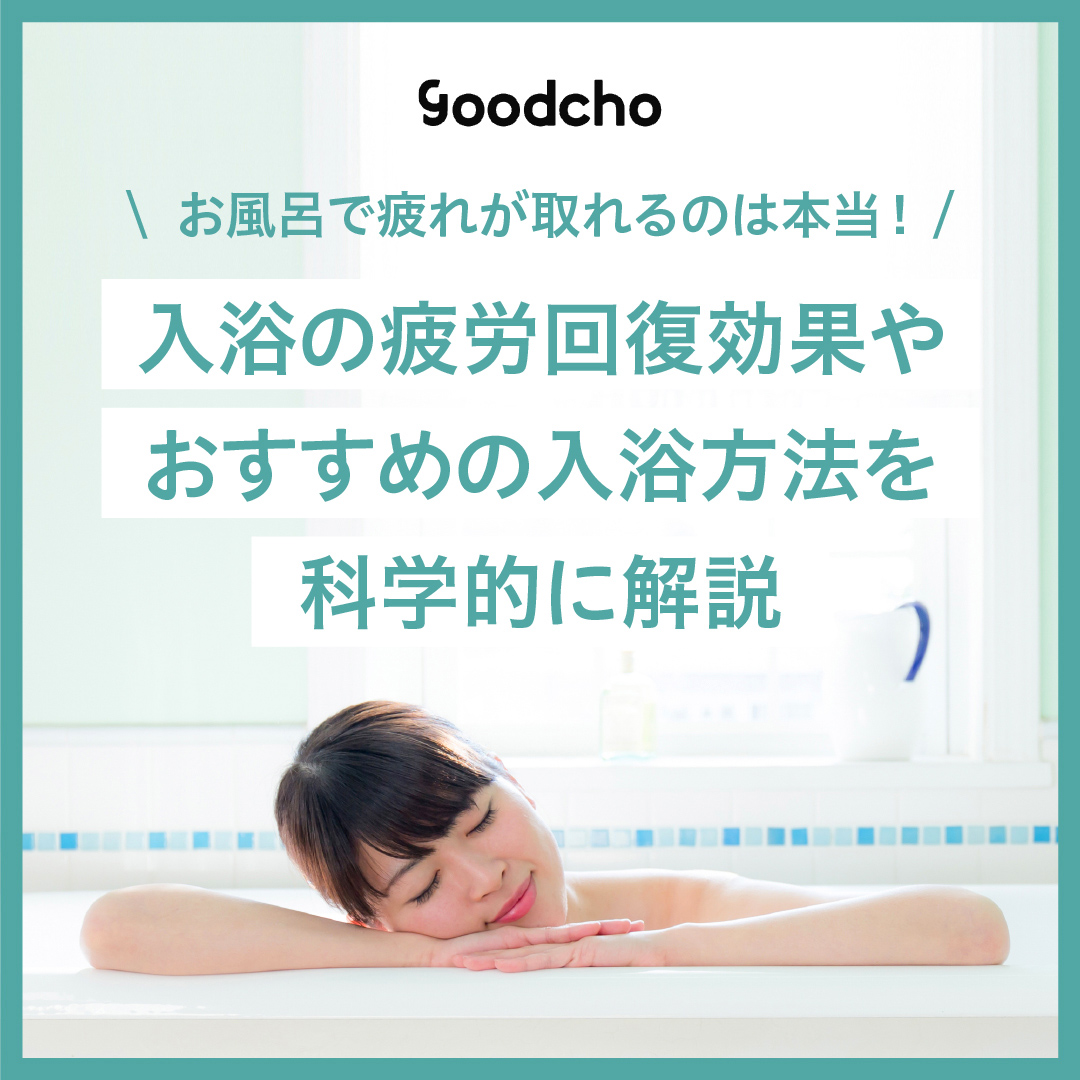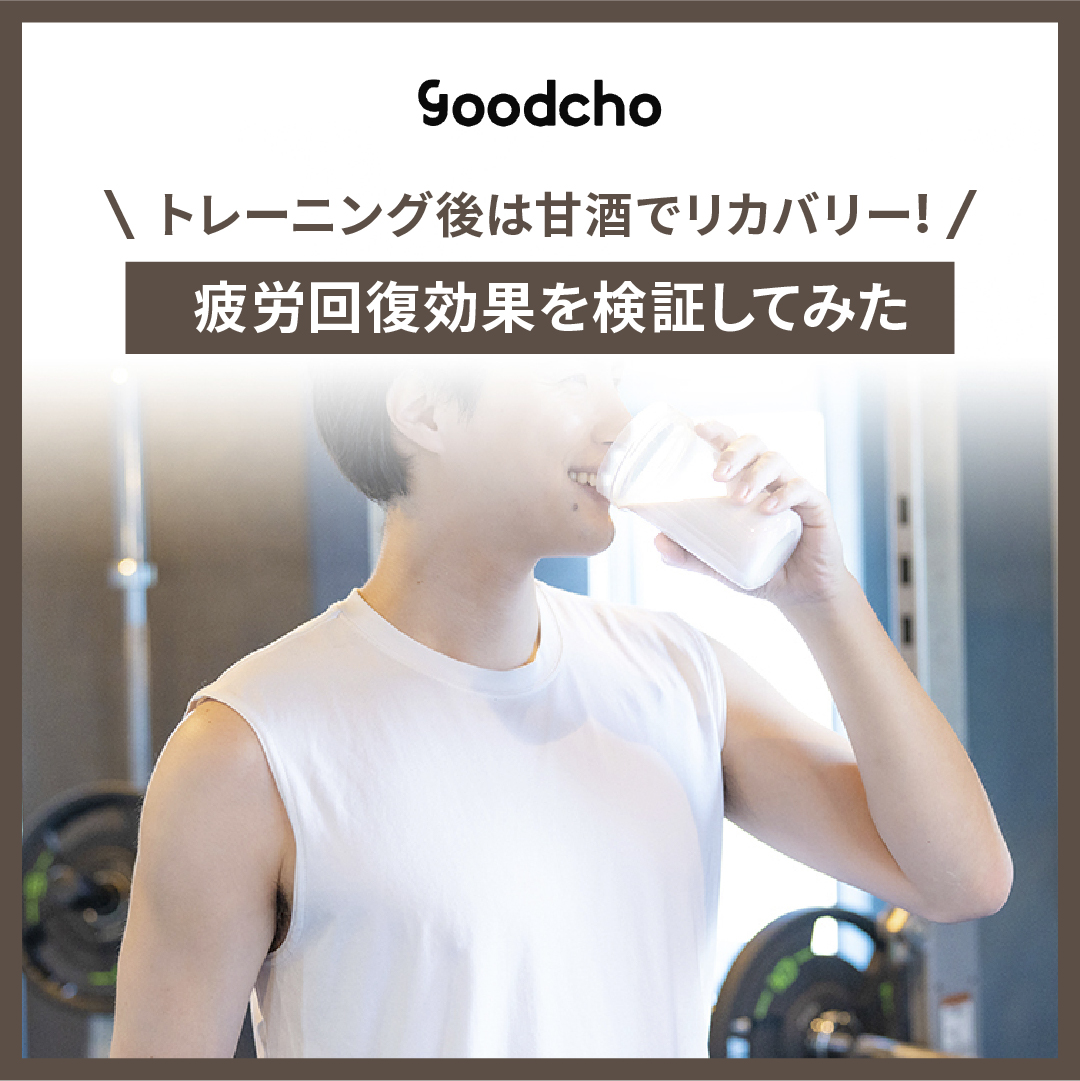日本食になくてはならない「麹(こうじ)」。味噌や醤油、日本酒など、さまざまな発酵食品を生み出す原点となる存在です。実はこの麹、保存や風味づくりのためだけでなく、健康面でも多くのメリットが期待されています。この記事では麹の基礎と、そこから得られる代表的な健康効果についてわかりやすく解説します。
麹の基礎知識

「麹」とは、蒸した米や麦、大豆などに麹菌(アスペルギルス・オリゼ)というカビを繁殖させたものです。麹菌がつくり出す酵素により、デンプンやたんぱく質が分解され、旨味成分や甘味が生まれます。
なぜ“カビ”なのに安全なの?
世界には多様なカビが存在し、中には有害な毒素をつくる種類もあります。しかし、麹菌(アスペルギルス・オリゼ)は食品安全性が高く、有害物質を産生しない菌株が選別・利用されているため、安心して摂取できます。
麹菌は食品安全性が高く、国菌と呼ばれるほど日本の食文化に欠かせない微生物です。味噌、醤油、日本酒、みりん、甘酒など、麹を使わないと作ることが難しい発酵食品が数多くあります。
腸内環境を整える

麹菌の最大の特徴は多種多様な酵素を生み出す点です。デンプンを分解して糖化を促す「アミラーゼ」、たんぱく質を分解してペプチドやアミノ酸を作り出す「プロテアーゼ」などが代表的です。 これらの酵素が食材に作用することで、体内に取り入れたときの栄養吸収がスムーズになり、腸内での消化負担を軽減する可能性があります。
麹菌が発酵の過程で作るのは、酵素だけではありません。ビタミン類、アミノ酸、ポリフェノール、さらには免疫調節に寄与する多糖類など、健康維持に役立つと考えられている様々な成分が生み出されます。 (*1)
これらの機能性物質は、腸内環境の改善や抗酸化作用、免疫バランスの調整など、多岐にわたる健康効果をもたらすと期待されています。
生活習慣病のリスク軽減

麹発酵の過程で生まれるビタミンやアミノ酸、ポリフェノールなどの機能性成分には、抗炎症や抗酸化作用があるとされています。スタンフォード大学の研究では、発酵食品を多く摂る人はそうでない人に比べて腸内多様性が高く、炎症マーカーも低いことがわかりました。(*2)
慢性炎症が続くと、肥満や糖尿病、心疾患など生活習慣病を引き起こしやすくなります。麹を活用した味噌や醤油などを日常的に摂取することで、これらのリスクを軽減する可能性が指摘されています。
免疫バランスへの影響

免疫細胞の7〜8割は腸で働いているといわれており、腸内環境の良し悪しがアレルギーや感染症に対する抵抗力に大きく関わります。麹由来の発酵食品には、βグルカンや発酵多糖類など、免疫調節作用をもつとされる成分も含まれます。(*3)
このような成分は腸管の免疫細胞を刺激してIgA抗体の産生を促すなど、免疫の過剰反応を抑えつつ必要な防御力を高めると考えられています。たとえば、醤油由来の多糖類がアレルギー性鼻炎の症状を緩和したという報告もあり、麹がもつ免疫への影響は今後さらに注目されるでしょう。
まとめ
麹は、日本独特の発酵食品文化の基盤となる微生物の集合体ともいえます。保存や旨味だけでなく、腸内環境の改善や生活習慣病リスクの低減、免疫バランス調整など、多方面での健康効果が期待されています。 ただし、麹を使った発酵食品の中には塩分や糖分が多いものもあるため、摂りすぎには注意が必要です。バランスの良い食生活の中で麹を上手に取り入れ、体の内側から健康をサポートしていきましょう。
引用文献
*1: Lee da E et al. (2016). Molecules, 21(6):773.
*2: Wastyk, H. C. et al. (2021). Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status. Cell, 184(16), 4137-4153.e14.