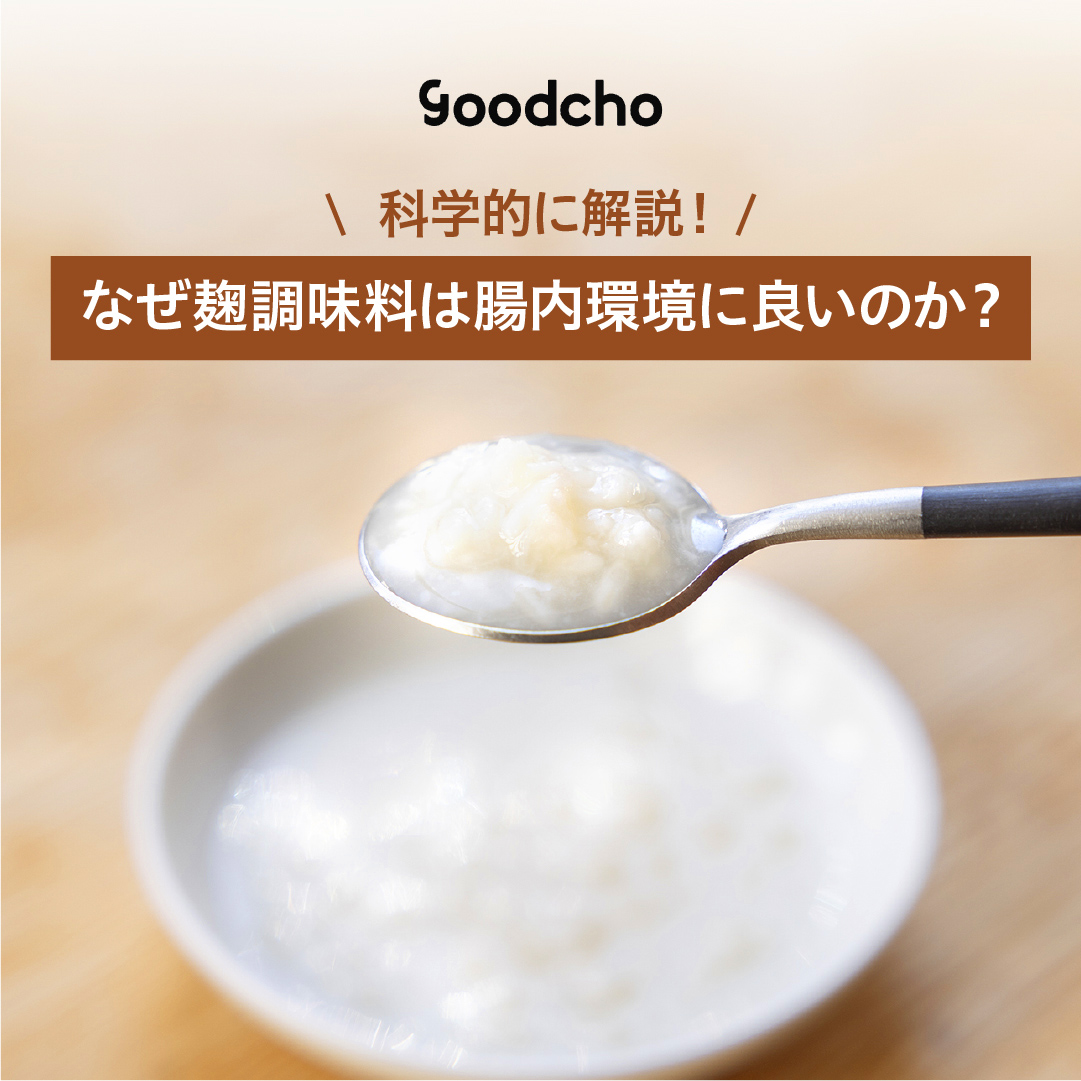「甘酒」は、豊富な栄養素を含んでおり、古くから「飲む点滴」として親しまれてきました。米麹や酒粕を使った甘酒には、腸内環境を整える力があることが分かっています。今回は、その栄養素や腸への効果を基礎から解説します。
甘酒とは?その栄養素と特徴

甘酒は、お米を原料とした飲料で、古くから健康飲料として愛飲されてきました。甘酒には米麹甘酒と酒粕甘酒の2種類があります。米麹甘酒は、お米を麹菌で発酵させたもので、デンプンを分解して作られるブドウ糖やオリゴ糖、ビタミンB群を豊富に含んでいます。一方、酒粕甘酒は、米・麹・酵母・水を発酵させて日本酒を作る際に生じる副産物である酒粕を主原料とし、これに水と砂糖を加えて煮溶かして作る甘酒です。発酵過程で生じたタンパク質や食物繊維、β-グルカンなどを多く含み、栄養素の宝庫です。
米麹甘酒、酒粕甘酒のどちらも、腸内環境を整える役割を果たし、日常的に摂取することで健康維持に寄与します。
甘酒の腸内環境への効果

甘酒に含まれるオリゴ糖や食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内フローラを改善します。実際、米麹甘酒を毎日摂取した研究では、排便回数が増加し、腸内細菌叢が改善されたことが示されています (*1)。腸内環境が整うことで、便秘が解消され、消化機能が向上することが期待できます。
甘酒を日常に取り入れる方法と注意点

毎朝一杯の甘酒を飲むことで、腸内環境を整え、栄養補給も一石二鳥で行うことができます。しかし、甘酒には糖分が多く含まれているため、摂りすぎには注意が必要です。特にダイエット中の方や糖分を制限している方は、摂取量を調整することが大切です。また、甘酒を飲むタイミングとしては、朝食時や間食として摂取するのが理想的です。
江戸時代の甘酒売りと夏バテ対策

ところで、甘酒の歴史をたどると、江戸時代には「甘酒売り」が町を練り歩いていたという興味深い話があります。当時の日本では、暑い夏に栄養不足になることが大きなリスクでしたが、甘酒の豊富な栄養素はまさに“救世主”だったわけですね。「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価が高く、夏場の熱中症対策としても重要な飲み物だったとされています。
甘酒売りは、町の人々が体力を落とさないよう、冷たい甘酒を手軽に提供していたそうです。現代の私たちの感覚でいえば、街角の自動販売機感覚に近いかもしれません。水分補給や栄養補給、さらには夏の疲れを吹き飛ばす一杯として親しまれた甘酒は、今でも同じように夏バテ防止に役立ちます。暑い日にはちょっと冷やして飲むと、やさしい甘さとすっきりとした口当たりで、ほっと一息つくことができますよ。
まとめ
甘酒は、腸内環境を整える力を持つ飲料であり、毎日の習慣として取り入れることで、便秘の改善や腸内フローラのバランスを整えることが期待できます。豊富な栄養素を含み、腸活をサポートするための素晴らしい選択肢となるでしょう。ぜひ、朝に一杯の甘酒を取り入れて、健康的な腸内環境を作り上げてみてはいかがでしょうか。
引用文献
*1: Kurahashi, A., Enomoto, T., Oguro, Y., Kojima-Nakamura, A., Kodaira, K., Watanabe, K., Ozaki, N., Goto, H., & Hirayama, M. (2021). Intake of Koji Amazake Improves Defecation Frequency in Healthy Adults. Journal of Fungi, 7(9), 782. https://doi.org/10.3390/jof7090782
*2:Kageyama, S., Yoshinaga, E., Touyama, Y., Inoue, R., Minami, T., Matsumoto, M., Kawamura, I., Naito, Y., & Irie, Y. (2021). Effects of Malted Rice Amazake on Constipation Symptoms and Gut Microbiota in Children and Adults with Severe Motor and Intellectual Disabilities: A Pilot Study. Nutrients, 13(12), 4466. https://doi.org/10.3390/nu13124466