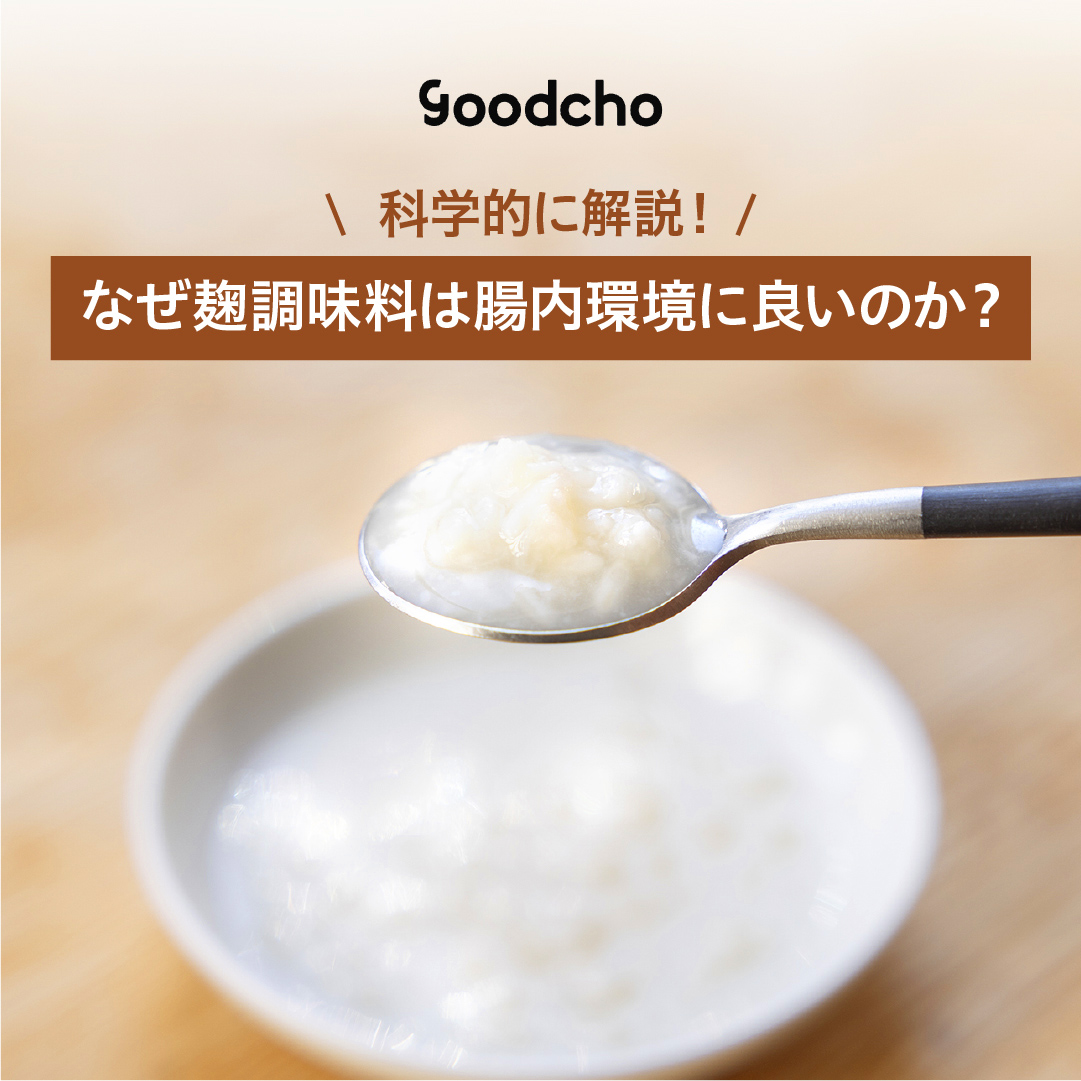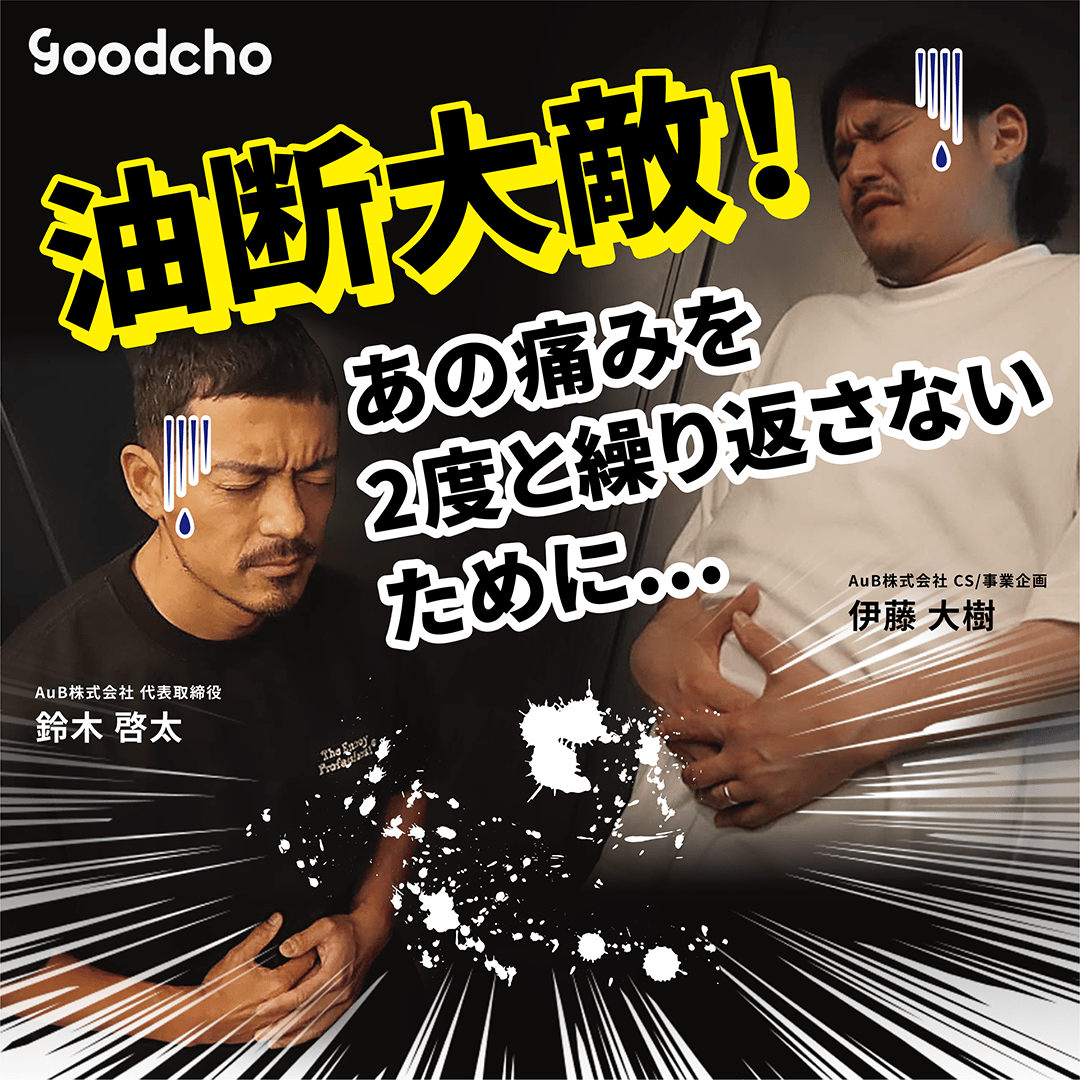日本の伝統的な発酵技術を活かした麹調味料(塩麹や醤油麹など)は、ただの流行ではなく、その科学的根拠に基づいた「腸に良い」効果が注目されています。本記事では、麹調味料がどのように腸内細菌に働きかけ、健康維持に寄与するのかを、わかりやすく解説します。
麹調味料とは?

麹調味料は、米や麦、大豆などから作った麹を基に、塩や醤油と混ぜ合わせ発酵させた調味料です。たとえば、塩麹は麹に塩と水を加え熟成させることで、食材を漬けると旨味と柔らかさを引き出します。また、醤油麹は、醤油と麹を組み合わせることで、より複雑で深みのある味わいを実現しています。
麹調味料の特徴
麹調味料には以下の特徴があります。
- 麹菌が作る働きにより、食材のたんぱく質やデンプンを分解し、消化吸収をサポートする
- 麹菌が発酵の過程で生成した有用物質(ポストバイオティクス)が含まれている
- 伝統の技法により、素材本来の旨味を引き出し、風味豊かな調味料となる
プロバイオティクス&プレバイオティクス効果

腸内環境の改善には、腸に有益な菌(プロバイオティクス)と、これらの菌の栄養源となる成分(プレバイオティクス)の両面からのアプローチが効果的です。麹調味料は、この両方の役割を担う可能性があります。
プロバイオティクス(善玉菌)
長期熟成させた味噌、醤油、塩麹などには、乳酸菌や酵母が含まれており、摂取後、腸内で一時的に善玉菌として働くことで、悪玉菌の増殖を抑制する効果が期待されます。
プレバイオティクス(善玉菌のエサ)
麹菌が産生するオリゴ糖や糖脂質は、消化酵素で分解されにくく大腸まで届くため、ビフィズス菌などの善玉菌を増やすエサとして働く可能性があります。(*1)
腸内細菌叢への具体的な影響

実験的研究では、麹由来のグルコシルセラミドがマウスモデルにおいて、Blautia属の有益菌を増加させる効果が報告されています。Blautia属は腸内の有害菌を抑制し、整腸作用に寄与することから、腸内環境の改善に重要な役割を果たします。(*1)
さらに、人を対象とした発酵食品全般の研究では、腸内の善玉菌多様性の向上とともに、短鎖脂肪酸の産生が促進されることが明らかになっています。短鎖脂肪酸は、大腸のエネルギー源として働くだけでなく、腸管バリアを強化し、悪玉菌の抑制にも貢献します。(*2)
麹調味料の取り入れ方と注意点

腸活に麹調味料を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。
加熱しすぎない
麹調味料は加熱により酵素が失活するため、調理の仕上げに加えるなど、できるだけ酵素の働きを保つ工夫をしましょう。
塩分管理
麹調味料は塩分を含むため、全体の塩分量を意識して使用することが大切です。
摂りすぎに注意
発酵食品であっても、過剰摂取は胃腸に負担をかける可能性があるため、少量を毎日続けることを心がけましょう。
その他の発酵食品との組み合わせ
納豆、ヨーグルト、漬物などと併用することで、さらに多様な菌やプレバイオティクスを摂取し、腸内環境への相乗効果が期待できます。
まとめ
麹調味料が「腸に良い」とされるのは、麹菌や乳酸菌、酵母といった有益な微生物と、善玉菌のエサとなるプレバイオティクス成分を同時に取り入れられるためです。科学的研究によれば、麹調味料の摂取は腸内細菌叢の多様性向上や短鎖脂肪酸の産生促進に寄与し、腸内環境の改善に効果的であると示唆されています。日常の料理に塩麹、醤油麹、甘酒などを取り入れて、内側から健康な腸環境づくりを目指してみてはいかがでしょうか。