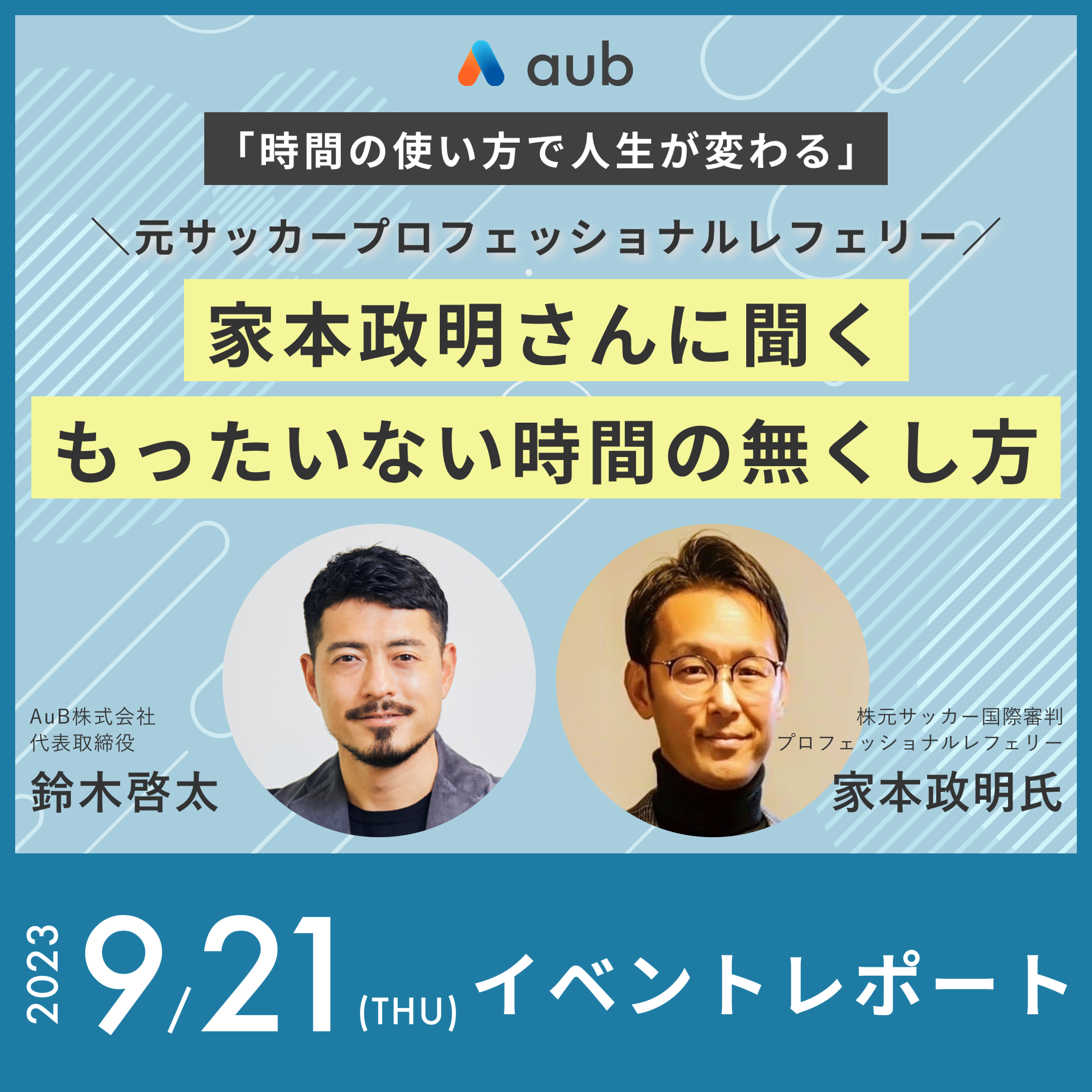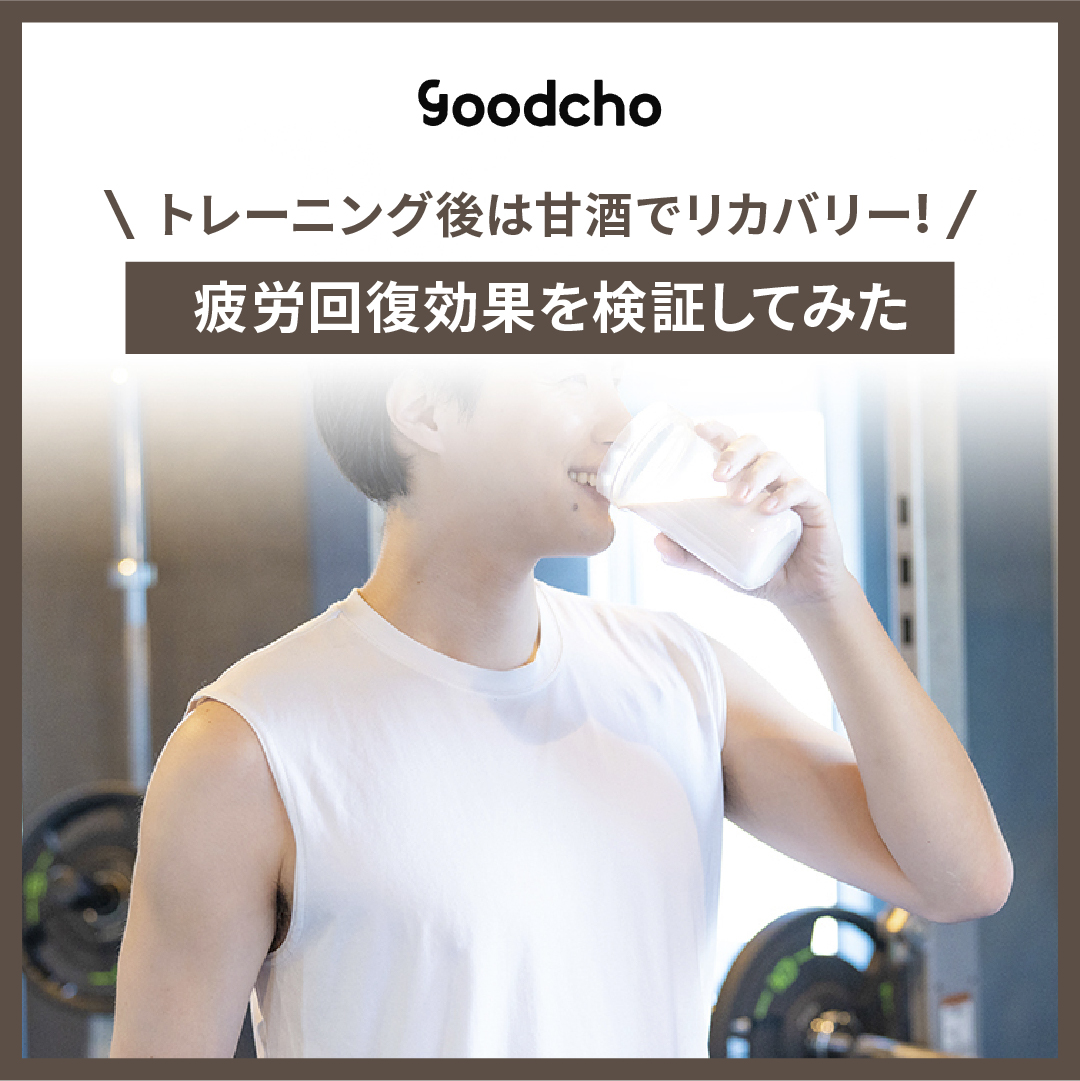長時間のデスクワーク、靴の形、歩く機会の減少など、これらの外的要因が積み重なって、私たちの「足指」は本来の働きを発揮できていないと言われています。足指が使えない状態は、姿勢やバランスにも影響し、日常の疲れやすさにもつながる可能性があります。本記事では、足指の機能が低下する背景と、今日からできる見直しのヒントをやさしく解説します。
足指が”使えなくなる”とは?

足指が地面にしっかり触れず、浮いたような状態になることを一般に「浮き指」と呼びます。実際、成人女性の約7割、男性の約6割、以上に足指の地面への接触不良が確認されたという報告があり(*1)、世代を超えた身近な課題といえます。足指が働かないと、結果として、姿勢の乱れや疲れやすさにつながる可能性が指摘されています。
なぜ現代人は足指を使いにくくなったのか

現代人の足指が使いにくくなった背景には、いくつかの要因があります。まず靴の構造として、転倒防止などの目的で「つま先が上がった形状」の靴が多く、指先が自然に浮きやすくなっています。また、デスクワークの増加で座っている時間が長くなり、歩く機会が減少していることも大きな要因です。これにより足の筋力、特に足指や足裏の細かな筋肉を使う機会が少なくなっています。
さらに、運動不足により下半身の筋肉全体の活動量が下がり、指先で地面を「蹴り出す」動作が弱まりやすくなっています。加えて、サイズや足の形に合わない靴を選ぶことで、指の動く範囲が狭まり、地面を感じる感覚も鈍くなってしまいます。
足指機能低下がもたらす連鎖反応

足指が使えない状態になると、体に様々な変化が連鎖的に起こります。まず足指が使えないことで、かかとに重心が偏ります。次に、体の中心部分にねじれが生じ、姿勢の乱れや歩き方の非効率化という流れで、日常の疲労感やパフォーマンス低下につながる可能性があります。また、子どもの成長期では足の機能の発達を妨げる懸念があり、高齢者では転倒リスクに関わる可能性も示されています。
今日からできる見直しポイント

足指の機能を改善するために、今日からできることがいくつかあります。
まずは靴を見直しましょう。つま先に十分な空間があり、指が上下左右に動かせるものを選ぶことが大切です。サイズはつま先の余裕だけでなく、足の幅や甲の部分のフィット感も確認しましょう。
日常生活では、指先の小さな運動を取り入れてみましょう。タオルを床に置いて指でたぐり寄せる「タオルギャザー」や、足指でグー・チョキ・パーをする運動など、短時間でも効果的です。テレビを見ながらの「ながらケア」がおすすめです。
また、機能性のあるインソール(中敷き)の活用も有効です。足の骨(立方骨や踵骨前部)を適切に支えつつ、足指が動く空間をつくるタイプは、足指の働きを引き出す設計が特徴です。
続けるコツと注意点

改善に取り組む際は、小さく始めて継続することが大切です。靴の見直しや指の軽い運動から始めてみましょう。違和感が強い場合は無理をせず、頻度や時間を調整してください。
ただし、痛みや腫れ、しびれがあるときは、自己判断で無理に運動せず、専門家に相談することをお勧めします。この記事の内容は医療行為を目的としたものではありません。
まとめ
足指が「浮く」背景には、靴の構造や歩く機会の減少といった外的要因が重なっている可能性があります。まずは靴と歩き方、そして指先の小さな運動から始めてみましょう。足指がしっかり使えるようになると、重心の移動がスムーズになり、毎日の立つ・歩くがよりラクになることが期待できます。できることから無理なく始めてみませんか。
引用文献
(*1)江木順子(2011)「浮き趾の実態とつまずき・転倒の関連」早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士論文